2023.3.10
日本の“早すぎる上場”はスタートアップエコシステム全体にとっての損失(前編)

※本記事は2022年10月13日、DIAMOND SIGNALに掲載された寄稿記事に一部加筆・修正を加えたものです。
本記事では、シリコンバレー在住で日米のスタートアップ環境に精通したマネージングパートナーの渡辺大が、日本のスタートアップの早期上場に対する課題提起と具体的な解決策について、前編・後編と2回にわけて解説。前編では、「スタートアップエコシステムの役割」と「早期上場が事業拡大の足かせとなるケース」について論じます。
起業家不利の投資環境はVC業界全体にとっての損失
日本のスタートアップ投資契約は欧米に比べると往々にして起業家に不利な条件に偏りがちだ。50年かけて今の仕組みに進化した米国と比べれば市場は進化の初期段階。これが、「起業家不利」な投資環境の一因になっている。
本質的には「ビジネスリスクを取って、ものすごく大きな成長を目指す」というのがスタートアップ、特にベンチャーキャピタル(VC)から資金を調達する(VC-Backed)スタートアップの肝である。それができない投資契約を結ぶということは、起業家のみならず、関わるみんなにとって損になることだ。
スタートアップ投資で、起業家個人の金銭的リスクを上げることで投資家を守ろうとすると、逆に起業家が思い切ったチャレンジがしにくくなり、大きな成功を妨げることに繋がりかねない。これは単純に「起業家不利、投資家有利」ということではなく、投資の性質をローリスク・ローリターンに振ってしまうことになる。
投資のサイクルが何度も何度も回るようになれば、大成功したスタートアップが用いた投資契約など資金調達のノウハウがまねされるようになり、自然淘汰の結果、市場は進化していくはずだ。起業家がよく分からずに契約について悩み、事業立ち上げに使わなければならない貴重な時間を浪費する今の日本の状況は、VC業界全体にとっても損失だ。今回はその例の1つとして、日本のスタートアップの早すぎる上場を取り上げ、なぜ早期上場がお勧めできないのか、4つの視点から説明したい。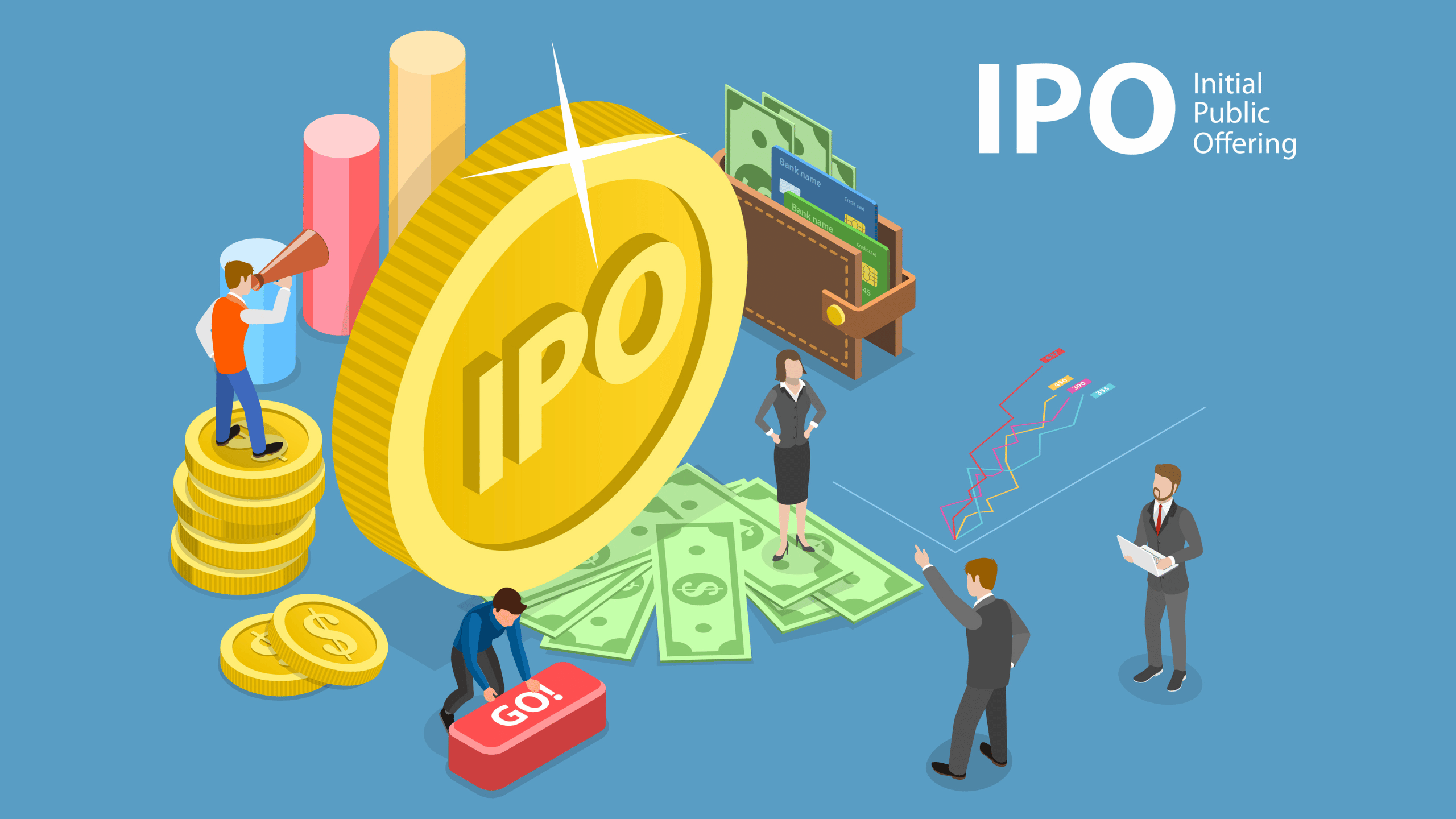
1.「大きなリスクを取って大きく勝つ」スタートアップエコシステムの役割
投資家の立場で見たとき、投資資産の種類(アセットクラス)には、上場企業への投資や債券・不動産など、さまざまなリスク・リターン・プロファイル(どのくらいのリスクを取ってどのくらいのリターンを目指すか)が存在する。
その中でVC投資というのは、業界の構造を変えるイノベーションで急成長を目指すビジネスに対する投資であり、失敗する可能性も高い。さらにファンド運用期間の約10年間は投資がロックアップされ、現金化されないという特殊性もある。つまり性質上、超ハイリスク・ハイリターンなアセットクラスである。
そんな性質を持つ業界に期待される役割とは、「リスクを許容して」、「イノベーションを先導する」ということだ。
1980年代以降、米国の大企業は株主至上資本主義を掲げてきた。結果として、R&D投資がなくなり、大企業は衰退し存在感を失っていった。今振り返ると、これは米国資本主義の大きな凋落(ちょうらく)を特徴付けるトレンドの始まりだった。
大企業が空洞化して、実質的に成長しなくなった代わりに台頭したのが、VC投資を活用して成長するスタートアップエコシステムだ。これは米国の経済にとって非常にラッキーなことだった。大企業が技術開発に投資しなくなった分、10年かけて社会の大変革をもたらす投資がスタートアップに対して行われ、スタートアップエコシステムが大きなイノベーションをけん引することになる。その結果、GoogleやApple、Microsoftといった巨大IT企業、あるいはSpaceXやTeslaのような先進的企業が誕生した。
そして、その変革の裏には死屍累々(ししるいるい)と失敗したスタートアップがある。ほとんどのスタートアップが失敗すると言ってもいい。「業界構造を大きく変えるビジネスを、失敗を恐れず10年かけて行う」というスタートアップへのR&D投資が、エコシステム全体で繰り広げられてきた。
スタートアップが大企業のR&Dと違うのは、起業家がオーナーシップと金銭的インセンティブを持っていること、投資家に評価されないビジネスは資金が尽きて早々に淘汰されること、そしてスタートアップ同士の熾烈(しれつ)な戦いが繰り広げられる、ということ。従来のR&Dとは比べ物にならないほどの生産性とスピードで巨大なイノベーションを起こす、というのがスタートアップエコシステムの役割なのだ。
米国のVC投資がもたらした結果を見れば、そのことがよくわかる。2004年から2014年の間にVCが行った2万1000社への投資のうち、65%はVCにとって損に終わっている。25%が5倍以下のリターンだ。20倍以上の利益をもたらしたのは1.5%、50倍以上は0.4%。VCは20倍、50倍のリターンを出すほんの少数の投資によって、損を取り返し、利益を上げている。ほんの一部の大成功によって、半分以上の失敗を取り返すことが、統計上最初から期待されているわけである。そのためには、「そこそこの成功」を狙うのではなく、常に業界構造を変える大ホームランを狙って投資しなければならない。
結果として、米国では大企業が軒並み苦戦する中、世界規模で革新的なビジネスが次々に誕生した。VCが支援する企業の成長がなければ、米国の経済は惨めなまでに低迷していたはずである。
大企業の低迷は米国以外の先進国でも起こり、各国が米国型のスタートアップエコシステムを立ち上げようと必死に追随した。イスラエルを皮切りに、中国、南米、欧州にと、次々とスタートアップエコシステムが立ち上がってきたのは、ご存じの通りだ。
2. 早期上場は海外展開による事業拡大の足かせとなる
米国で毎年生まれる新興企業のなかで、VCから資金を調達する企業は、ほんの0.5%程度しかない。それなのに、2019年の時点で米国の上場企業の半分以上がVCが支援した企業であり、時価総額に占める割合は8割近い。上場企業全体のR&D支出のうち、なんと9割近くがVCが支援した企業によるものだ。
世界で見ても、時価総額上位10社のうち、5社がVC支援企業だ(2022年10月7日時点)。米国だけでなく、世界の経済をVCから出資を受けた会社が引っ張っているといってよい。Microsoft、GoogleやAppleの製品が現代人の日常生活に深く溶け込んでいることからも、それが実感できる。
一方、日本の上場企業で上位を占める企業はどうだろうか。上位50位の中でVCが支援したといえる企業の数は、たったの1社のみだ。それも、ソフトバンク(現・ソフトバンクグループ。VC支援企業ではない)と米Yahoo!(VC支援企業。Verizonによる買収を経てAltabaへと再編された後に解散)がジョイントベンチャーとして設立したヤフー(現・Zホールディングス)をカウントした場合である。直接VCから資金調達した会社は、時価総額上位100社の中でもゼロだ。
国内時価総額の上位を占める伝統的大企業の多くが世界で名を知られており、米国のVC支援企業が世界の経済成長をけん引する中、日本のVC支援企業の存在感がここまで小さいのはなぜか。
僕は、日本のスタートアップが上場をゴールとして重視しすぎていることが一因だと思っている。事業ステージの早い段階での上場を求められた結果、事業規模の拡大に苦労しているのではないか。
日本のアーリーステージスタートアップのピッチにも「〇〇年上場予定」というスライドがほぼ必ず入っていますが、なくなるべきと個人的に思います。
— 渡辺 大 @ デライト・ベンチャーズ (@dai_WTN) July 5, 2022
Remove that 'exit strategy' slide from your pitch deck https://t.co/vw2nGOursY via @techcrunch
日本の多くのスタートアップは上場するまでは国内市場に集中して、上場後に海外を目指す戦略をとる。しかし上場会社であることは海外展開には大きな足かせにもなりうるのだ。僕の前職でもあり、デライト・ベンチャーズのLPでもあるディー・エヌ・エー(DeNA)もその罠にはまった。
DeNAはVCの支援を受け2004年に上場し、海外展開を目指した。当時DeNAの主戦場だった日本のモバイルインターネットは世界的に見ても最も発展していたため、その勢いを利用して海外の市場にも同時に投資することとなったのだ。
株主は国内の業績が順調な成長を見せている間、海外展開を歓迎した。だが国内市場が一旦飽和し始めると、そのプレッシャーが高まった。米国のマーケットは日本に比べて規模が大きく、その分、投資額がかさむ。当時の米国事業は、長期的な投資計画を要するフェーズだった。そのため日本の四半期や年単位の利益の見通しによって、米国への投資を抑えたり短期的な売上を絞り出したりしなければいけないこともあった(注:渡辺は当時、DeNAの海外事業責任者として海外進出を担当していた)。
早期に上場した日本のスタートアップが海外展開に苦労する、典型例とも言える。国内市場に最適化されたチームやプロダクトから脱皮して海外展開を目指すのは「第二創業」と言っていいほどの痛みを伴う。また長期的な投資計画が必要であり、短期的な時間軸で事業を評価する公開市場の株主とは相性が合わないことが多いので、上場のデメリットが際立つポイントだ。本当に世界規模のスタートアップを目指すなら、上場のタイミングより前に海外展開を行うかどうかは、起業家が意識すべきポイントだ。
<後編に続く>
日本の“早すぎる上場”はスタートアップエコシステム全体にとっての損失(後編)







